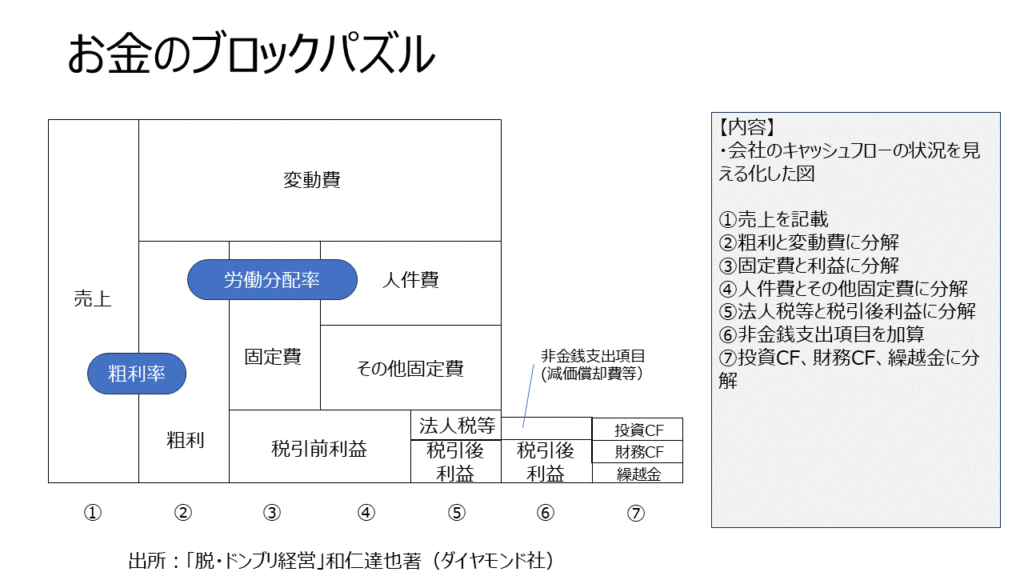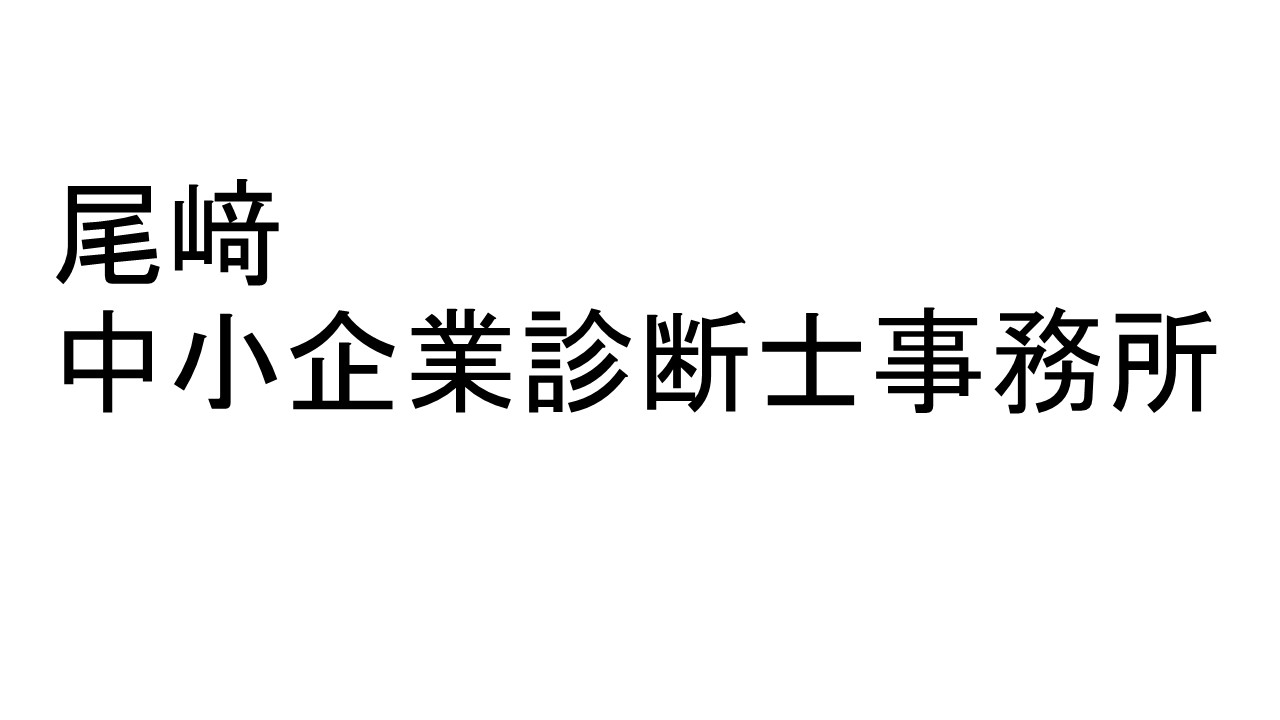皆さん、こんにちは。前回ご紹介したお金のブロックパズルを用いて、お金の流れの全体像を把握することができました。今回は「入りと出のバランス」についてお伝えしたいと思います。今回も「超★ドンブリ経営のすすめ」和仁達也著(ダイヤモンド社)を参考にさせていただきます。
皆さんは、これまでこんな疑問を持ったことはないでしょうか。
「売上はあるのに、なぜ利益が少ないのだろう?」
「うちの会社では、適正な人件費ってどれくらいだろう?」
「借金はいくらまでしてよいのでろう?」
もしかしたら、多くの方がこれまでの経験則や勘でご判断されていたかもしれませんが、「客観的な裏付けが欲しい」という方は、3つの指標(モノサシ)をご活用いただければと思います。それは、①「粗利率」、②「労働分配率」、③「借入金の完済年数」です。
①「粗利率」
粗利率は、一般的にサービス業で70-90%、小売業で20-50%、卸売業で20%以下と業種によってさまざまですが、この粗利率をいかに高めるかが重要になります。
しかし、売上がアップしても利益が思うように上がらないことがあります。「商品構成が変わって利益率の低い商品の割合が高まった」、「変動費(外注費など)が増えた」、「値付けを安くし過ぎた」、「値引きを多発した」などの原因が考えられます。
粗利率を上げるには、「取引企業に価格交渉や契約条件の見直しを要請する」、「安易に値引きしない」、「適正な価格設定を行う」、「材料や商品の仕入れは、量とタイミングをコントロールする」、「外注委託していたものを内製化で対応する」などの対策が必要です。自社が最も価値を生む仕事・商品に集中するマインドが重要かもしれません。
②「労働分配率」
労働分配率=人件費÷粗利 ですが、会社が生み出した粗利のうち、どれだけを人件費として分配しているかを示します。目安として50-60%なら妥当な水準、40%台なら良好、60%以上なら危険信号と言われています。重要なことは「必要な利益を生むには、労働分配率は何%以内でなければならないか?」と発想することです。一般的には「人件費はより小さく、粗利はより大きくする」と考えがちですが、「人件費は大きく、その分、粗利はもっと大きくする」という方向性もあります。社員と会社がともに成長・発展し、利益を共有できるのはこのスタンスかと思います。
③「借入金の完済年数」
「借入金はいくらまでならOKなのか?」、難しい質問ですね。借入金の金利の支払いは経費ですが、元本返済は経費ではなく、税金を払った後のキャッシュフローからでしかなされません。したがいまして、年間の営業CF>年間の返済額 となる必要があります。
また、今の借入金の総額が年間の営業CFの何倍(何年分)になっているかも重要な指標です。借入金の総額÷年間の営業CF の値が10倍なら、10年で完済できる収益力があるということです。この数字を押さえておく必要があるかと思います。皆様の会社はいかがでしょうか。